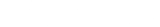ノーハウへの軌跡<4>
みなさんこんにちは
40年程前の新聞記事であるノーハウへの軌跡もラストとなりました。
会社の規模や社員数は当時とは変わっておりますが、志は当時と同じようにこれまでも、これからも持ち続けていきたいと思います。
それではノーハウへの軌跡 ラスト はじまりはじまり

「パールトーン加工は検品に始まり検品に終わる」
社長・國松照朗の口グセだ。
加工に先だち、依頼品をあらゆる面からチェックする。汚れはないか。加工に不適な染料が使われてはいないか。金銀糸・箔に問題はないか。シミがついていても加工 できないわけではないが、汚れたままの現状を固定することになる。これでは何のための加工かわからない。まず、シミ抜きなどをしてから加工するようすすめる。
加工の適合をきびしくチェックした結果、15%前後は返品されることになる。もしこの検品をやらないで加工してしまえばどうなるか。手描きの高級品など、とんでもないところに染料がついていることがある。仕立ての段階であわてることになるだろう。それを仕立て前に発見すれば、簡単に処理できる。この検品は外科医が手術前に行う消毒にあたるだろう。消毒しなければ手術できないわけではない。ところが、消毒なしの手術を強行すれば、患者には化膿などの“後遺症”が現れる。これを熟知している医者は、消毒なしの手術は怖くてやれない。
おかげで市田など得意先では、「パールトーンの検品だけでもメリットが高い」という。手間も省けるし、商品管理の一助にもなる。こんな加工以前のきめ細かい処理も、パールトーンの声価を高めてきた。
キモノを守るパールトーン加工は、こうした“ノーハウへの軌跡”でその地盤を固めてきた。一社だけで、この業界を開拓してきたといってもいい。その自信と実績が、二代目社長・國松照朗を、後発メーカーに対して寛容にさせていた。加工技術を競い、その発展につながるなら、キモノ振興のためにも喜ばしい。それに「全呉服をうち一社でやるのは不可能」でもある。
ところが、つい数カ月前、さすがの國松もあきれはてるような“事件”に直面した。得意先から見せられた一枚の宣伝チラシ。うっかりすると、國松でさえ「わが社のものかと間違えそうな類似作」なのだ。冒頭の部分だけを紹介してみよう。
「もし、キモノにおしょうゆやコーヒー・お酒など、水性のものがついたときは/〇例えば、おしょうゆがついた場合/①キモノについたおしょうゆを、タオルに吸い込ませながら、軽くふき取ります。」(パールトーン)
「もし、キモノにおしょうゆやコーヒー、お酒など、水性のものがついたときは/◇例…おしょうゆがついたとき/①キモノについたおしょうゆを、タオルに吸い込ませ、軽くふきとります」(某社)
比較するまでもない。そっくり同じといっていい。単純なのかイラストもほとんど同じ。印刷文字の色の配合まで同じという念の入れようだ。ダジャレでなく、パールトーンのコピー(文案)がそのままコピー(複写)されている。あまりのことに、持ち込んだ得意先氏は「ニセものか」と一笑に付した。しかし、客にはまぎらわしい。現に“被害者”も出ている。「商法うんぬん以前に商道徳にもとる行為」だと、國松よりも取引関係者の方がエキサイトしてきた。
思えば半世紀前、先代社長の國松勇が細々と始めたパールトーンも、いまやそっくりそのままマネをした類似品が出現するまでに育ったのだった。國松照朗が好きな1914年のキャデラックのコピー「ペナルティ・オブ・リーダーシップ」(人の上に立つものの辛さ)が、現実のものになってきた。トップブランドは質でもトップでなければならない。宣伝コピーは同じでも、わずかに二十八万円の機械で副業的にやっている“類似コピー社”と、三千万円‐五千万円の設備投資で八人の検品員の前処理から始まるパールトーン加工とか同じわけはない。
伝統産業であるキモノの灯を守る。キモノ振興の陰の力になる。-いずれもパールトーン社の“誓”である。國松は「キモノの振興を心がけ、それを期待する一人として振興策を提言」してきた。しかし、企業としては、現実のキモノ離れを無視することもできない。式服の主役だった留袖、中振などがドレスに代わりつつある。そこにシルクが進出してきた。
「シルクが主体となると、キモノが持っていた弱点を洋装界でもそのまま持つことになる。パールトーン加工に対する要望も必然的に出てきて(洋装の分野も)手がけざるを得なくなっている。
パールトーン加工は、シルクなど動物性繊維には100%の威力を発揮する。過去にイタリア直輸入の某一流ブランドのドレスを手がけた実績がある。すでにシルクの広幅ものに、パールトーン加工を利用している洋装メーカーもある。そうしたメーカーのひとつのK商事では、今秋、シルクを中心とした新作を発表するが、そのすべてにパールトーン加工をして、新しいブランドで売り出す予定だという。“ノーハウへの軌跡”は、さらに間口を広げようとしている。
【サンケイ新聞掲載記事】